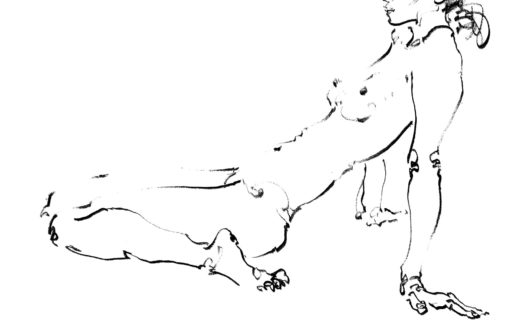1979年夏、画家の卵だった大庭豊さんは、フランスの小さな町、コールマールの修道院にいた。
「その修道院にグリューネヴァルトの『キリストの処刑』っていう、イバラが全身に刺さって、血がしたたり落ちてる作品があって、うーん!すごいな!と見惚れていたんです。
そこにドイツ人の家族が来て、男の子が『もういい!行かない!』って泣き出したんですね。小学二、三年生ぐらいの。お父さんはいい絵だから見なきゃって言うんだけれど、男の子は絵の迫力に圧倒されて『行かない!行かない!』って駄々こねて床に座り込んでる。そういう場面を直接体験して、作品って凄いんだな!って思いました。
芸術の凄さ。芸術がある時には恐怖になり、ある時には希望になり、ある時には物凄い喜びになっていくっていうのを、直接フランスに行って、体験して、自分が一端でも担えればという気持ちになったんです。」
それから20年以上、大庭さんはフランスで画家として過ごし、1999年、福岡県那珂川市南畑の南面里(なめり)地区にアトリエジョンヌを構える。
室内に飾られているのは抽象画。見ても「分かる」という感じにはならない。
「これで人とコミュニケーションをとれるなんてすごいな」と思っていたら、大庭さんは熱を帯びた口調で、こんな話を聞かせてくれた。
「作品っていうのはコミュニケーションじゃなくて、見る人がそれを鏡にして何を感じるかなんです。自分の鏡なんで、見えない人にはなんにも見えない。ところが見える人には、ものすごい深さを持っていて、自分をどんどん発見させてくれる。」
実は全く同じ話を、別の作家さん(抽象作品をつくる石川幸二さん)のところでも聞いていた。期せずして繰り返された鏡の話に「僕も見てみたい!」という気持ちがふつふつと湧く。
見える人にはどこまでも自分を映す鏡。
いったい、どうしたら、そんな鏡がつくれるのだろう。
この問いに対し、大庭さんは、ある生徒さんとのやりとりを教えてくれた。
「僕の生徒がこんなの描いてましたって、まるで印象派のような作品を持ってきたことがあったんです。で、『あーうまいですねぇ、でも、ここまで描けたらもうちょっとなんとかできなかったかなあ』って言うと『えっ、どうしてですか。みんなからいいって言われる。先生はそう思わないんですか』って聞いてくる。」
印象派というのは、19世紀後半にパリで起こった芸術運動。
素人の僕でも、マネ、モネ、ルノワールといった作家や絵のことは知っている。
まるで印象派のように描けているというのは、相当上手なはずだ。
なのに、どうしてその絵を大庭さんはいいと言わなかったのか。
「印象派に見えるのがいいと思うんだったら、あなたは150年前に生きてるんだよ。そう話したんです。印象派の絵は、印象派の時代に、印象派の人たちがやったことなので、あなたが描いてるのは、あなた自身ではないんじゃない?と伝えました。」
いまの時代に生きているあなたが描くのは、そんな絵でいいのか?
そう問われた生徒さんは、激しく葛藤したそうだ。
みんなからいいと言われていたのだから、容易には受け入れがたかっただろう。
けれど、彼女は三年ほど大庭さんに付いて問答を繰り返した後、いまは全く違った「いい絵」を描いているという。
「うまいのといい絵とはぜんぜん違うんですね。これを説明するのは大変なんですけど、でも、やっぱりいい絵を僕は描きたい。僕自身は時代を捉えることができるかどうかによって、作家であるのかないのかが試される気がするんですよ。」
作家であるかどうかを左右する「時代」。
その例として先生は、東日本大震災の頃の出来事を話してくれた。
「震災から3年後に生徒たちを連れてローマに行って、お茶を飲んでたんです。そしたら、恰幅のいい御老人がとっとっと近づいてきて『イタリア語わかりますか』って。『わかりますよ。大丈夫ですよ』って答えると『このたびはご愁傷様でした。』って直接言われたんですよ。『今度のことは、我々イタリア人もものすごく心配してる』って。
ビッッックリしましたー!
僕の中では日本で被害があって、日本の中だけで話すことなのかなと思っていたら、世界中が震災のことを話して、心配している。これが時代なんですよ!世界中がおなじなんです!」
世界中がおなじように感じていること。それが時代。
作家は、その時代をどう見ているのかを描く。
大庭さんの描いた東日本大震災の絵は、なんとも言えない迫力があって、悲しくて、じっと見ていると仕事が続けられなくなりそうだった。
と、思いのほか硬派な記事になっていることに気づいて、驚いている。
話をうかがったときの大庭さんの感じと、合わない。
お話を聞いていて本当に楽しかった。
時間があっという間に過ぎて、何度も大声で笑ったし、芸術を語る時のあふれんばかりの情熱にこちらも胸が熱くなった。
そして、そうそう、これは「南畑」美術散歩のインタビュー。
作家さんみんなに南畑の魅力を聞いていて、大庭さんも家を決める前、老婦人に丁寧にお辞儀された話や不在時に竹の子やじゃがいもの袋が置いてあった話なんかを面白おかしく語ってくれたのだけれど、僕がいいなあと思ったのは、インタビューが終わってコーヒーを飲んでいたときの、このやりとり。
――フランスに帰ろうと思ったことはないんですか。
「帰りたいです。」
すがすがしいほどの即答。そういう人もいるよなあと思った。
南面里の山の上に吹く風も心地よく、僕は大庭さんのことがますます好きになった。